人間の「差別」の幕は降りないのか 『喜劇 人類館』
- 2022/11/20
- エンタメ・スポーツ

いつしか笑いは引きつっていく
公演終了後には、日替わりで演出家や出演者、そのほかゲストを迎えたアフタートークも開催された。5日は演出の知念あかねさんと、東京工芸大芸術学部写真学科准教授の小原真史さんが登壇した。小原さんは会場のなはーとで人類館も含めた「人間の展示」をテーマにした企画展をキュレーションしており、今回の上演場所となった小劇場の扉を開けると目の前が企画展会場になっていた。
過去の公演を劇場でも映像でも観てきたという小原さんは、今回公演について「遠めの席から観たんですが、モンタージュやスローモーション、ストロボのなど演出技法で現在の中にどんどん過去が呼び込まれて、まるで映像を観ているようでした」と感想を口にした。「色んなバージョンを観たんですが、観るたびに印象が違います」とも話すと、こう付け加えた。
「東京で観た時には最初けっこう笑っていたんですが、だんだんその笑いが引きつってきて、最後は笑えなくなりました。今日沖縄だとまんじりともせず、全編ずっと真剣に観ていました。どの時代に誰と、どこで観るかということを投影してしまう、鏡のような作品だと思いました」
加えて小原さんは、人類館に“陳列”されていたアイヌの人たちが「自らの意思と目的を持って参加し、内地(としての日本)に同化しつつある自分たちをパフォーマティブに演じていたということに着目する必要があります」と指摘。「彼ら彼女らを被害者としてしか見ないことこそが、差別なのではないでしょうか」と疑問を投げかけた。

「沖縄は自ら『人類館』になっていないでしょうか?」
あかねさんは稽古で台本を読み込む中で、歴史や沖縄について「ちゃんと知らないことは怖いことだな」ということを何度も実感したという。その上で、現在の沖縄が「観光立県」として“売り出して”いることは「自ら進んで『人類館』になっていないでしょうか」と疑義を呈した。
また、正真さんが戯曲『人類館』を書いたタイミングや動機を巡って、会場から出た質問に答えたあかねさんは「人類館が書かれたのは私が生まれた年で、まだ母のお腹の中にいる時だったんです。『お腹の子のために何かを残したい』ということで書き始めたと聞いています」と説明。
沖縄の本土復帰50年というタイミングにも触れつつも「今回の上演のタイミングは必ずしも復帰50年を明確に意識したわけではないんです」とし、「きっかけはあくまでコロナ禍だったんですよね。こうして今上演しているのは“時代がそういう風になった”という感覚です」と感慨を語った。
■関連リンク
☆差別を考えるための“起爆剤”に 11月3日から『喜劇 人類館』 ‖ HUB沖縄
☆喜劇人類館 16日から無料公開 琉球人も展示された事件題材 ‖ HUB沖縄
☆博覧会に内在する権力と欲望の眼差し なはーとで企画展「帝国の祭典」 ‖ HUB沖縄



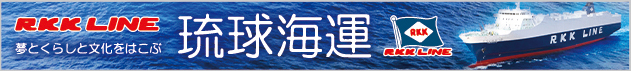








-1-150x112.jpg)










-1-150x112.jpg)
