喜納昌吉、復帰を語る「自分たちの文化で興奮しなさい」
- 2022/5/4
- 社会
その“勃起運動”を「沖縄だけではなく日本もしないといけない」と喜納は強調する。「ペリーが黒船で来航した時、日本人は右のゴールデンボールを落としたんだよ。そして戦争に負けてマッカーサーが来た時に左のゴールデンボールも落としてしまった」。自文化への誇りを、男性の持つ生命の源に例えて話す。
その中で喜納は、沖縄文化を背負って本土に打って出て、人気を博した。自文化を受け継ぎながら発展形を作り上げた自負がある。そういった気概を日本人と日本文化にも求める。「僕は日本が落としたゴールデンボールを2つ預かってるわけさ。全部で4つ持ってるんだよね。だから、県外で演奏する時は『2つの玉を返しに来たんだよ』と、ジョークでね」
喜納の預かる「2つの玉」は、7つ揃えば願いが叶うドラゴンボールさながら、人々が追い求めているものなのかもしれない。
文化と経済の自立

復帰から現在に至る50年間、未だに一貫して課題に挙げられているのが「沖縄の自立」だ。経済的な自立という意味合いで使われることが多いこのキーワード。喜納は沖縄の自立をこのように考えている。
「どこかで思考停止があるんですよ。沖縄社会にある構造的な病を見抜く力がないと。例えば、沖縄には県庁があるのに、(政府の出先機関の)沖縄総合事務局もありますよね。これは二重行政で半植民地ですよ。テレビ番組を見ても、前みたいに沖縄で作った番組が放送されなくなっています。もっともっと自分たちの文化を持ち、自分たちの音楽を持ち、自分たちの言葉を持って、国の予算に依存しないで自分たちの財政を作る。そうなると自由な発想ができるでしょう」
「そういった意味では、僕は自立しているよね」と喜納は言う。「自分の音楽があって、それで経済的に成り立っているし、政治家の時も含めて自分の言いたい放題しゃべっているし。僕は妥協しないよ」
“遊び人”喜納昌吉
取材後、那覇市国際通りにある喜納のライブハウス「チャクラ」に招かれ、一緒に向かった。フロアの奥には赤いビリヤード台が。「球撞きする?」と誘ってくれたその瞬間には、すでにボールをナインボールの形に並べ始めていた。
「僕はこうやって、よく遊ぶんだよ。今の人は遊びが足りない」

1ゲームが終わり、私がトイレに立っている間も、喜納は一人でビリヤードを続けていた。「遊ぶ」という言葉が「遊んでる場合じゃないよ」「この遊び人め」などと否定的な意味合いで使われることも多い昨今。しかし、心の余裕の中から遊びが生まれ、遊びの中から文化が育ってきたことも確かだ。
日々目まぐるしい現代社会の渦にいる私たちが復帰すべき場所は、そんな遊び心溢れる場所なのかもしれない。
そうこうしているうちに、バンドメンバーが顔を出し始めた。喜納がメンバーにこう告げた。「もう少ししたら、練習しようね」。今日の練習も楽しみだ、と言わんばかりの表情だった。



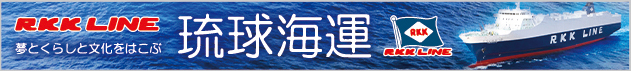



















-1-150x112.jpg)
