- Home
- 暮らし・教育・子育て
- 設備は不十分、方法も手探りで教員は疲弊 オンライン授業の困難さとは
設備は不十分、方法も手探りで教員は疲弊 オンライン授業の困難さとは
- 2021/11/9
- 暮らし・教育・子育て

前出の男性教諭の学校では当初低学年でのオンライン授業は見合わせており、タブレット端末でドリル形式の簡単な問題のやりとりに留めていたが、報道を受けて学校判断で急遽実施することになったという。何の準備もない段階から1週間程度で児童たちの家庭のWiFi環境の有無について調べ、Zoomの操作を急ごしらえで学び、うろ覚えのまま児童たちにも使い方を指導した。子どもたちを指導する立場の教員としては、理不尽とも言える状況の中でも「できない」とは言えない。
必死でオンライン授業期間を乗り切ったが、授業の内容を「全然分かってない子が明らかに多かった」ため、学校が再開されると全く同じ内容をリアル授業で繰り返した。「子どもたちのことを考えると、まだ分散登校で同じことを2回やった方が良かったと考えています」
「クオリティが低い」とクレームも
挙げ句、教育事務所からは「クオリティが低い」「学びになっていない」「教員の口調が強い」などと保護者たちからのクレームが多数届いていたという通知がきた。男性教諭は「心の中で膝から崩れ落ちましたよ。短期集中で時間も体力も浪費してめちゃくちゃに頑張ったんですけど、結局疲弊しただけという感じでした」と苦笑いする。
一方で「保護者の皆さんにはとても助けられたんです」とも語る。デジタル端末の操作がままならない児童たちがオンラインで学習するには、保護者の協力と理解が不可欠だ。「我々も手探りでしたけど、子どもたちも保護者の皆さんも初めてのことで戸惑いはかなり大きかったと思います。そんな中でのオンライン授業は、保護者無しには成り立たなかったのも事実ですから」
利点もあった。不登校の子どもが、顔は出さないものの音声だけの形で授業に参加することができたのだ。保護者からは「オンライン授業をやったことで『これなら参加できる』と子どもが喜んでいる」という声も届いたという。
「子どもと簡易的なコミュニケーションをとることで安否確認もできます」と男性教員は話す。授業や勉強の話をすると苦しくなるという子どもの声を受けて、今日したことや食べた物を教え合うなど、取り止めのないやりとりを容易にできるようになった。「この点は歓迎すべきですし、色んな可能性をさらに模索すべきだと思います」
現場負担の解消と実のある体制づくりを
10月に入ってからは感染者数は徐々に落ち着き、11月には時短も解除され「コロナ前の日常」に近づきつつある現状だが、今後「第6波」がやってこない保証は無い。
通常授業に戻った学校現場は日々の業務で忙しく、次のオンライン授業を見据えた準備の動きは見られないという。常時その場凌ぎの対応では、おそらくいつになっても十分な環境は整わないだろう。それは、子どもたちの学びの機会の喪失を意味する。教員の過重負担と学校間での落差を解消しつつ、オンライン学習をきちんと実のあるものにするための体制づくりが必要だ。









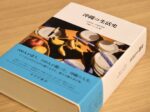












-1-150x112.jpg)
