独自の出口戦略、学校早期再開 浦添市長インタビュー
- 2020/5/11
- 政治

新型コロナウイルスの脅威が県民生活を直撃する中、医師会に協力して沖縄県内で初めて病院以外の場所でPCR検査を導入したり、学校再開を他市町村より早めて実施する構えを見せたりするなど、独自の対応が際立つ市町村の一つが浦添市だ。
5月9日には、浦添市独自の出口戦略を県内市町村の先鞭をつける形で発表。11日から4段階に分けて自粛体制からの解除に向けた道筋を示した。
松本哲治浦添市長は、行政の長としてどのような観点から対策を講じているのか。感染防止や学校再開、経済対策などへの考え方を聞く。
PCR検査場を1週間でスピード設置できた背景
浦添市医師会は2020年5月1日、沖縄県では初めて病院以外でPCR検査が実施できる「浦添地区新型コロナウイルス検体採取センター」を稼働させた。三密を避ける観点からドライブスルー方式で、現状で1日あたり5検体程度の検査を実施でき、今後は20検体の実施体制を目指していく。設置の動きは那覇市、沖縄市でも続いた。
場所は、浦添市の中央部・仲間地区に位置する市民ホール「アイム・ユニバースてだこホール」の地下駐車場だ。周辺には市役所、市立図書館、ANA SPORTS PARK浦添(浦添運動公園)など公共施設が多く立ち並ぶ。駐車場は半地下構造となっており通気性が確保されている。
この検体採取センターの話が持ち上がったのは「4月の終わり、25日ぐらいだった」と、松本市長は振り返る。
「浦添市医師会から『やりましょう』とアクションがあり、市としてはそれに全面的に協力した形です」
発案から約1週間のスピード実施については、「浦添市は(那覇市など中核市レベルの都市と比べて)比較的人口規模が小さく、周辺市町村と合同ではない市単独の医師会があったため、意思決定を早く進められた」とのことだ。
実施場所は当初、運動公園や屋内運動場、保健相談センターなど複数の候補が挙がったが、専門的な見地を持つ医師会に選定を任せた。てだこホールの駐車場は①場所そのものの知名度が高く案内しやすい②駐車場敷地が一方通行で誘導しやすい③一番近い民家から250m離れている―という要素が決め手になった。
「PCR検査をできるだけ多く実施することで、『もしかしたら自分は感染しているかもしれない』という不安の声に応えていく必要が行政としてあると考えています」

県内自治体初の独自出口戦略
松本市長が5月9日に発表したのが、「うらそえリハビリ計画」だ。新型コロナウイルスによる自粛体制からの独自の出口戦略である。4月末から内部で検討を重ねたところ、「県や那覇市と足並みをそろえるべきではないか」との声もあったが、市長が主導して決めた。
この計画では、11日から4段階に分けて自粛体制を解除するという。
【第一段階 5月11日~】
市役所を通常通りの勤務体制とし、休校の延期が続く学校は登校日(課題配布日)を設定する。また、飲食店については、昼間営業は3密などの感染対策を徹底することで自粛解除とし、夜間営業もこれまでの8時の閉店を10時へと拡大する。
【第二段階 18日~】
国の中間評価を考慮しながら、公立の小中学校を分散登校などの措置を講じながら始業し、保育園は通常開園、学童クラブの通常受け入れを始める。飲食店の夜間営業は3密などの感染対策を徹底しつつ自粛を解除する。
【第三段階 25日~】
県の判断も見極めながら、出張などの移動自粛の解除
【第四段階 6月1日~】
国や県の緊急事態宣言が解除されるか見極めながら、観光も含めた移動の自粛を解除する。
こうした計画はあくまでも現時点での計画であり、今後の状況の変化次第では、躊躇することなく、再自粛要請などの変更を行うという。
市の発表によると、前述の検体採取センターが稼働していること、浦添市には観光客向けの宿泊施設が少ないこと、子どもの人口が多いなどの特徴があることに加えて、多くの市民が協力的・献身的に助け合う環境があることなどから、専門家の意見も参考にしながら、こうした独自の取り組みを進めることにしたという。
急ぎたい学校再開、脆弱な県経済 感染予防と社会的影響のはざま
今回の対応で、市長自身が一番頭を悩ませているのが学校再開についてのタイミングだ。
「子どもたちのことだけに、親の状況も含めて考えなければならず、一番センシティブな問題だと考えています。学校を開けるか閉めるかというのは、社会的な影響やインパクトがとても大きい。学校だけの問題ではなく、保育所・学童クラブをどうするかといった議論にもなり、保護者が仕事へ行けるのかどうかという意味では、各家庭の収入の問題にもなります。
沖縄県の経済事情は脆弱ですし、特にひとり親世帯は追い込まれやすい傾向があります。感染拡大を防ぐための医学的な見地や子どもたちの教育という見地以外にも判断せざるをえない材料はたくさんあるのです。
私としては、子どもたちの感染予防と休校措置による社会への影響とでバランスを取りながら、行政が一定のラインで見極めをつけて学校をできるだけ早く再開させなければいけないと考えています」
再開前倒しに現場は「混乱している」との声も
しかし、このことは学校現場からの強い批判を浴びている。
ある30代の男性教諭はこう話す。
「早く学校再開に向かいたい気持ちは同じですが、教室に子どもたちがいること自体、感染リスクが高まります。給食となるとなおさらです。県立学校や他の市町村は21日再開なのに、浦添だけが18日再開というのは、状況をきちんと見極めたものなのか。18日に再開するという根拠をはっきりさせてほしいです」
また、再開にあたって一度に教室にいる児童数を半分にするとされているため、その対策にも追われているという。
「クラスを2つに分けて、同じ日の午前午後で分けるか、2日に1回ずつの登校にするか両方見越して対応せざるを得ないなど、現場は混乱しています」(同前)
無難に足並み揃えず「現状を考慮して判断するのが市町村の仕事」
学校再開の見極めについて松本市長は、「様々な見極め方があると思うが、県の専門家会議で示されたロードマップ(目安や見通し)を参考にしつつ決定する」としている。
ロードマップでは、入院患者数と1週間の新規患者数がともに全県で14人、さらに感染経路不明の患者が少なくとも7日間確認されない場合に「段階的な活動再開」に移るとされており、そうなれば、学校に関しても少人数授業の実施が可能となる。
沖縄県によると、5月10日現在、県内の確定患者は4月30日以降、一人も出ていない。浦添市内については、4月20日に感染が確定した30代男性を最後に新規の感染者は出ていない。
「浦添市は最後の感染者確認から2週間が経過しているという面もあり、学校再開を判断できる根拠はあります。しかしゴールデンウィークの連休があったことから(感染状況の様子見で)一旦延期にしている状況です。沖縄県や近隣市町村の『21日再開』に合わせるのは無難かもしれませんが、この現状を鑑みれば、21日まで待つ根拠はあるのか、ということです。そこを独自に考慮して考えていくのが市町村の仕事です」
休校によって家庭で子どもを見なければならず、仕事に行けずひっ迫している市民から、対応を求める声が連日多くあることも事実だ。
「休業補償はもちろん大切ですが、学校も保育園も学童も、感染を防ぎながらできるだけ早く“同時に”再開し、新型コロナウイルスの感染拡大以前の状況に戻すことが最も目指すべき道筋だと考えています」
学校がストップすることで、子どもたちに与える影響も考慮している。
「家庭訪問もできないため、休校となっている期間に、子どもたちがどこに行っているのかも分からず、(学校などが)親と連絡が取れない家庭もある。表面化はしにくいがDVなどネガティブなことが家庭で発生しているということも、想像以上に多いのではないかと思っています。そんな子どもたちを大きく抱きしめてあげるのは学校だと思います。安心して給食が食べられて、話しかけてくれる先生がいる。私は社会において学校が持つ絶対的な存在感や子どもたちを包み込む地域として器のような機能を今回のコロナ禍の中で痛感したんです。だから私は、学校を早く再開した方がいいという意見です」
「他府県より衝撃は大きい。県は全国に先駆けてリーダーシップを」
前述の通り、沖縄県内の新規感染者数はピーク時と比較すると低調に推移しており、10日間連続(5月10日現在)でゼロとなっている。これを松本市長は「嬉しい誤算」と捉える。
「気を緩めてはいけませんが、学校再開など収束に向けての出口戦略を、沖縄県が独自で練り、判断を示していい、というのが今の数字ではないでしょうか。感染者数が減らなければ出口戦略に向けた話すらできません。
沖縄の場合、主要産業である観光が大きな痛手を受けているため、他府県と比べても衝撃の度合いが違います。医療崩壊や新規感染を抑えながら、全国よりも早くリーダーシップをとっていくのが県に求められていると思います」












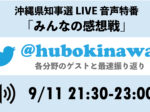








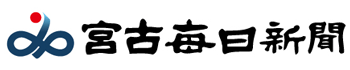


-1-150x112.jpg)
