写真家、映画監督、俳人など 90年代生まれの表現者が視る沖縄
- 2023/1/28
- 社会

写真家・上原沙也加の新作写真展『眠る木』の関連トークイベント「沖縄 で/から 語ること」が昨年12月24日、那覇市牧志のFoto Space Reagoで開催された。上原の他、オーガニックゆうき(小説家)、福地リコ(映画監督)、元山仁士郎(アクティビスト・研究者)、安里琉太(俳人)といった、90年代前半生まれの面々が登壇。司会は林立騎(翻訳家)が務めた。各ジャンルで活動する同年代の表現者がどのように沖縄を捉え、表象してきたのかをそれぞれの角度から語り合った。
写真展自体は昨年12月3日~29日に開催され、本イベントは同18日に開催された第一弾となるトークイベント『写真を編むこと』に続く第二弾として開かれた。
沖縄のリアルを表現に
沖縄で表現したり、沖縄を表現したりすることについて問われた写真家の上原沙也加は「大学で写真を学び出して、沖縄が大量に写真に撮られていることにすごく驚きました。写真史の中でも沖縄は得意な場所で、日本の中でも一番撮られている場所だと思います。沖縄の写真集だけで本棚が埋まるぐらい」と話しつつ「沖縄の写真はたくさんありますが、私が過ごしてきた『実感のある沖縄』はどこにも映っていないと感じていました。まだ映されていない領域が沖縄の中にもたくさんあるのではないかと思っています。沖縄って何なんだろうと東京に住んでいた時もずっと考えていました」と話す。
小説家のオーガニックゆうきは、沖縄を題材にした小説を書いた際、表紙デザインに関して一点だけ「分かりやすく青い空、青い海、ハイビスカス、みたいなものだけは避けてほしい」との要望を伝えたという。「私が幼少期に見ていた沖縄は、そんなに分かりやすい沖縄ではなくて、もっと生活に苦しくてお金を稼ぐのに四苦八苦していました。そんな景色にある意味で愛着を持っていたというか、沖縄の中でも埃をかぶったような地域を面白く表現できればという思いが、私のデビュー作『入れ子の水は月に轢かれ』が生まれたきっかけでした」と、自らが感じた沖縄を表現する。
俳人の安里琉太は、自らの祖父母が自ら進んで戦争体験を語りたがらなかった経験に照らし合わせて「戦後の沖縄には、ずっと喋れないことや、生き残った自分が語っていいのかという思いがある。書き急ぐということが必ずしも正しいわけではないと思います」と話した。

アメリカ視点しかなかった沖縄戦の記録映像
日米の外交史や冷戦史などの研究を行う元山仁士郎は、表現の中に「沖縄」を求められることについて問われた際「沖縄の市民運動が日米関係や冷戦にどのような影響を与えたのか、ということを問われることがあります。必ずしも影響関係にないこともある中で、沖縄を関連付ける言説が求められてしまうというギャップは感じます」と真っすぐに話し、「誰が歴史を書いていくかということを考える上で、沖縄出身の自分としては何かができたらと思っています」と目標を述べた。
映画監督の福地リコは「沖縄戦の記録映像はアメリカ側が残したものしか無くて、私たちは平和教育の場面でそういった沖縄戦の映像を見てきました。ただそれは、勝者の歴史であって、その目線でしか追体験ができません。このことを恐ろしく感じていました。沖縄の人が撮ってきた歴史はすごく最近のものです。私が映画表現に行きついたのは『自分たちでも撮らない?』という思いからでした」と話し、現在と未来をつなげる。

「実感のある沖縄」
上原は今月上旬、写真展と同名で自身初となる写真集『眠る木』(赤々舎)を刊行している。ふとした日常を切り抜いた作品ながらも、沖縄に住む者にとっては「いきいきとしたリアルな沖縄」を感じられる写真たちが、160ページにわたって収められている。
■関連リンク
上原沙也加『眠る木』 – AKAAKA



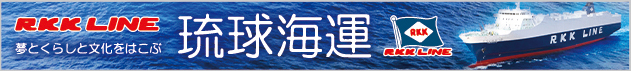



















-1-150x112.jpg)
