沖縄発の映画配給会社 アジア各都市巻き込み“文化の中継貿易”
- 2021/2/4
- 社会
「今の時代だからこそ、地方でもできるのだと思います」と話すのは、撮影・制作を行う中谷駿吾さんだ。情報社会の発達や海外渡航の敷居の低さで、地方拠点でもどんどんコンテンツの吸収や発信がしやすくなっている。
「台湾系移民」を追って沖縄へ

黄さんが沖縄で活動しているきっかけは「八重山の台湾系移民」に関心を持ったからだ。台湾移民をテーマに撮った長編ドキュメンタリー映画『海の彼方』(2016年)が同年の台北映画祭にノミネートされ、同9月に台湾公開を果たし、翌17年夏から日本でも公開された。
当時東京に住んでいた黄さんは、2013年から八重山を中心にフィールドワークを始め、約1年間で100人以上にインタビューを敢行した。「調べ始めたら終わらない」と、その膨大な成果をシリーズで公開する予定だ。今年は八重山ドキュメンタリーシリーズ第二弾として『緑の牢獄』を日台仏の合作で公開する。
同じく企画や製作に携わる作品として『月は何でも知っている』(アルゼンチン・台湾)、短編『草原の焔』(台湾・日本)も今年公開する他、2022年以降に完成する予定の4作のプロジェクトが進行中だ。その中には、沖縄戦で亡くなった人の遺骨収集ボランティアを続ける具志堅隆松さんを追った『骨を掘る男』も含まれ、沖縄ならではの作品も生み出している。
加えて、今は新型コロナウイルスの影響で開催が延期されているものの、国際映画祭「石垣島ゆがふ国際映画祭」の開催に向けても力を注いでいく構えだ。黄さんは「八重山諸島と台湾を結ぶ航路も拡充の動きがあり、今後は海外からも人が来やすくなると思います。東京などの映画祭とは違う視点の映画が集まる国際的なイベントにしたいです」と意気込む。
活発な沖縄映画カルチャー
沖縄県内の映画文化は、他府県と比べても充実しているという。菅谷さんは「(大手映画会社の直接の影響下にない独立した)ミニシアター系のスクリーンは、実は九州だと福岡と沖縄で1、2を争うぐらい多く、その数は増えています」と話す。県内では5館で計10スクリーンあり、それぞれが個性的な作品を上映している。同様に台湾にもミニシアターが増えているといい、黄さんは「特に地方で増えています」と、シネマカルチャーの国際的な変化を語る。

菅谷さんによると、映画業界全体の興行収入は2000年代に底をついて以降、上昇傾向にある。「若者がテレビを見なくなり、ネットフリックスやアマゾンプライムなどの映画のサブスクリプションを利用するようになった結果『映画を観る』という文化が再興しています。今の若者は“映画リテラシー”が高いです」



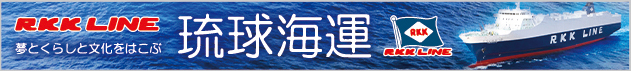














-1-150x112.jpg)
