常設展へ行こう 学芸員が語る魅力 〜県立博物館・美術館 美術工芸部門編(1)
- 2021/1/23
- 社会
刺繍の技法から過去の世界へ
数ある展示の中、與那嶺さんが紹介してくれたのは1500年代琉球の神女制度に基づいた「伊平屋の阿母加那志(あもがなし)正装」。
第二尚氏王統の初代・尚円王が特別に神職を与えた姉に贈った衣装で、簪や勾玉などと一緒に残されていた資料を基にして、現在の博物館オープン当初に復元したものだ。紅の下地に龍や鳳凰、草木や紋様の刺繍が施されており、島に残されていた文書と刺繍衣裳が、琉球王国時代の染織を紐解く上での大きな手がかりになったという。「神女という神聖な役職だったからこそ、代々受け継がれて残っていたのだと思う」

刺繍の模様復元は、着物の糸を通す穴のパターンを読み解いていくところから始まった。刺繍は従来のサンステッチと明らかに違い、西洋刺繍の「ヘリンボーン(=魚の骨)ステッチ」という刺繍の技法に似ていることが分かった。しかし当然、この当時ヨーロッパと琉球は直接的には交易していない。着物の形や下描きから、琉球で刺繍されたことはほぼ間違い無いので、輸入物ではない。
同時代の日本や中国にも同様の刺繍の作品はなかったが、世界規模で調べるとインドに同じ技法があった。当時の琉球はインドとも直接的に交易をしてなかったことから、與那嶺さんと復元に協力していた研究者たちは、インドからマラッカ(今のマレーシア)などを経由して技法が伝わったと類推している。「当時は着物の前面に刺繍をする流行があり、この刺繍の技法だと糸の量を節約できる上に重さを軽量化することにもなる」。
與那嶺さんに協力している研究者たちはこの技法を「琉球千鳥掛け」と呼んでいる。通常の千鳥掛け(ヘリンボーンより粗い針目)が細かく密に重なっており、同様の技法は世界を見回しても存在しないという。原型の千鳥掛けまたはヘリンボーンステッチは現在でもヨーロッパや中米、インドの織物に刺繍されているそうだ。
今では色彩素材の分析・研究が進み、当時の実物に更に近い形での復元に取り組んでいるという。「500年前の人たちがこの正装の人を見たら、どんな気持ちになっていたのかと考えると、どこまでも想像が広がる」

「展示品の全てが主役」
與那嶺さんは大学で織物を学んだ後、まず教員になり、転勤先として博物館に配属されて初めて学芸員の仕事を知ったという。ちょうどそのタイミングで博物館が織物専門の学芸員を探していたと後で聞いた。
「あの時に博物館に転勤しなかったら、今ここにいないはずね」とおどける。仕事で幸せを感じるのは「収蔵庫でデータ整理をしている時」だそうだ。
「長いこと忘れられていたものにスポットがあてられて、その技術が歴史を語る瞬間がある。こうした“もの”を通して発見していくことを私たち自身も楽しみながら、皆さんに伝えていくことにやりがいを感じる」と話す与那嶺さん。
展示品について「当時の形を残しているもの、復元したものも含めて、展示されている資料の1つ1つが物語を持っていて、その全部が主役。だからサッと見逃してほしくないですよね」と熱い思いを語って、微笑んだ。
◆開館時間や最新の企画展などの情報は、沖縄県立博物館・美術館(おきみゅー)WEBサイトへ
◆学芸員がそれぞれの専門について語るコラムも随時更新中



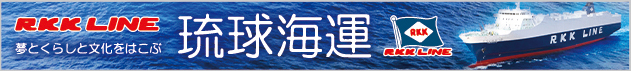



















-1-150x112.jpg)
