大開運シーサー職人の野望「首里城福光シーサープロジェクト」とは
- 2020/9/15
- 社会

沖縄に昔から守り神として伝えられるシーサー。そのシーサーを活用した首里城復興プロジェクトが立ち上がっている。その名も「首里城福光シーサープロジェクト」だ。
プロジェクトの発起人は、自らが「大開運シーサー」という縁起の良いシーサーを作る職人・宮城光男(みやぎみつお)さん。首里城及び首里城で使用されていた赤瓦と深い関りも持つ宮城さんは、首里城が焼失していく姿を眺めながら、このプロジェクトの発起を決意した。
「シーサープロジェクト」に込められた3つの想い

沖縄シーサー協会の代表でもある宮城さん。活動の一環として、首里城の焼失後すぐに立ち上げたのが「首里城福光シーサープロジェクト」だ。首里城の焼け残った赤瓦を有効活用し、高さ10mを超える巨大シーサーをみんなで制作しようというものである。
このプロジェクトには3つの想いがある。
ひとつは、沖縄シーサーの伝統に対する敬意である。沖縄でよく目にする、赤瓦屋根に取り付けられた漆喰シーサーは元来、家を建てる際に出る割れ瓦や余った漆喰から作られている。つまりシーサーは「ゴミから生まれた守り神」なのだ。「エコ」という概念がない時代からすでに、アップサイクル(単なる再利用ではなく元の製品より価値の高いものを生み出すこと)が行われていたこの歴史を、SDGsが推奨される時代にこそ継承するべきだと考えた。
2つめは、火災を納める守り神としての役割だ。現存する最古のシーサー(富盛の石彫大獅子 1689年~ 八重瀬町)は、火除けが目的で設置されたものであることから、首里城福光シーサーも同様に、火災からの復興と再発防止を願うシンボルにしたいと考えた。
そして3つめは、1992年の首里城復元の際、赤瓦を作った奥原 崇典(おくはら そうてん)さんへの敬意だ。宮城さんにとって奥原さんは師匠と呼べる存在。奥原さんは2014年に死去しているが、その赤瓦は特別な手法で作られており、同じ赤瓦は再現不可能とされている。その瓦をゴミ(産業廃棄物)にしてしまいたくないという想いがあった。





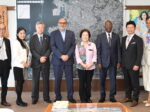












-1-150x112.jpg)
