【戦後76年 慰霊の日】出来事と記憶をどう語り継ぐか 映画のなかの沖縄戦①
- 2021/6/22
- エンタメ・スポーツ

梅雨明けも間近となり本格的な夏を肌に感じ始める頃、沖縄には暑さとともに独特の雰囲気が訪れる。1945年の4月から6月にかけて、民間人を巻き込んだ激しい地上戦で命を落とした人たちを悼む「慰霊の日」が近づくと感じる空気だ。今年は戦後76年になる。
沖縄戦という出来事とその記憶は、時間が積み重なって体験者の肉声が減っていくにつれて語り継ぐことの困難さがどんどん増している。そんな中、沖縄戦を知る/考えるための1つのきっかけとして、映画作品に注目してみたい。NPO法人「シネマラボ突貫小僧」代表で『沖縄まぼろし映画館』著者(當間早志共著)でもある平良竜次さんに話を聞いた。
体験してない世代がどう語り継ぐか

「沖縄戦も含めて、戦争を描いた映画には終戦後そんなに時間が経っていない作品でも、既に『どうやって若い人たちに伝えていくか』と試行錯誤しているのが演出から見て取れます。戦争を体験していない世代がどう語り継いでいくか、という問いに単純な正解はない。だからこそ、対峙し続けていかなければならない大きなテーマなのだと思います」(平良さん)
戦争に関連する作品は膨大な数があり、特に劇映画の場合は必ずしも歴史的事実を厳密に描いているとは限らないため、鑑賞する側の視点の設定や史実と照らし合わせるための知識も大事になってくる。受け手も能動的に臨まなければならないが、そうしてある程度“身構えて”作品を観ることで得られる気づきは多い。
沖縄戦描写の口火を切った「ひめゆり」映画

平良さんが手始めに挙げたのは「ひめゆりの塔」をテーマにした作品群だ。吉永小百合が出演する『あゝひめゆりの塔』(舛田利雄監督、1968年)が有名だが、終戦からまだ7年ほどしか経っていない頃に製作された『ひめゆりの塔』(今井正監督、1953年)が「おそらく初めて沖縄戦を正面から描いた映画作品としてエポックメイキングなものだと思います」と評する。
53年版は公開当時大ヒットし、社会現象になるほどの興行収入も上げた。製作当時は莫大な借金を抱えていた東映だったが、作品の莫大な興行収入で完済に至ったという。「本作は沖縄で撮影されてません。当時はまだ本土復帰どころか米軍統治が決定したという段階なので、戦争の悲惨さを描く作品は反米的なものになりかねないということも含めて、当然撮影隊は入れなかったんです」
作品のロケは真冬の最中、東京のオープンセットや千葉県の銚子海岸などで敢行され、画面によく目をこらすと吐息が白くなっているシーンもあるという。「役者はカメラを回す前に口の中に氷を含んで、息が白くならないように冷やしてたという話です」。
また、劇中でカメラが揺れるほどの爆薬を使って撮られている爆発シーンも見どころだという。「時期的に当然ですが、製作陣や出演者はみんな戦争を知っている“戦中派”。身を持って体験したことに基づいてリアリティを追求する姿勢も感じます」
映画作品そのものはもちろんだが、こうした小ネタ的なエピソードにも制作当時の時代背景についてかなりの情報量が詰め込まれており、それを浴びることができるのがひと昔前の映画に向き合うことの大きな楽しみと豊かさでもある。



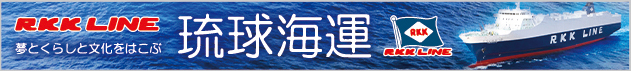














-1-150x112.jpg)
