コンクリート建築の父と大宜味大工のマスターピース 旧大宜味村役場庁舎
- 2020/11/5
- 社会
琉球も明治政府施行の廃藩置県に組み込まれ、「沖縄県」となって間もないころ。そのあたりからは政府主導の下、琉球の民の生活様式も徐々に底上げしていくべきだという流れとなってきた。
そこで沖縄本島北部の国頭郡には、建築技師として熊本県から清村勉という当時まだ20代の若者が担当者として赴任してくることとなる。
勉という名前の通り、この青年はもっぱら勤勉な若者で、当時ようやく日本に導入され始めたコンクリートの建築技術を独学で学び、自前で洋書を手に入れ研究に励んでいたという。ここにまず、彼がその後大きく推し進めることになる「洋風建築」の匂いが感じ取れる。
清村はまず、派遣された国頭の地で当時のあらゆる近隣の建築物を見て回り、木造茅葺きという耐久性の乏しさ、そして火災や台風被害、シロアリの被害などそれらを全て考慮した上で、ここ沖縄にこそコンクリート建築を導入すべきだと考えた。

材料となる資材も自分の目で見て自分の足で探し回り歩き、県内、特に北部にはコンクリートの材料となる砂利、砂も豊富にあることを確認。
さらに独自の研究でどの程度の材料配分量でどの程度の強度になるのか、またサビなどの腐食具合なども徹底的に調べ上げた上で、大宜味村役場をコンクリートで建築しようと試みる。
ただ、当時の現地住人たちにはもちろん理解し難い話で、石を使って建物を造るとはどういうことだ?となった。石で作る建物なんて、お墓くらいしか聞いたことないぞと。
しかし熱心な清村の説得に賛同し、沖縄初のコンクリート建築がここに始まったわけである。(実は旧庁舎建築より4年前に、同じく大宜味村に清村によって建てられたコンクリートの公設質屋が沖縄初であると言われている。今は現存しない。)
そしてここにもう一つ大きな偶然があった。
大宜見大工という存在
清村が派遣されたのが国頭であったこと、そしてその国頭の大宜味という村が「大宜味大工(うじみぜーく)」と呼ばれる県内でもトップクラスの技術を持つ大工の村であったいうことが大きかったのである。
当時の大宜味は耕作地として豊かな土壌とは言い難く、多くの男子は小学校を出ると、幼くして大工の弟子として働きに出ていた。そこで培った技術と彼らの生真面目さ、仕事の丁寧さ、そして一刻も早く家計を助けたいという思いから朝も夜も無く働いたと言われる。
その結果若くして棟梁になる者も多く、建築界隈では彼ら大宜味出身の大工がとても高く評価されていたという。
大宜味役場庁舎建設は、技師と大工、双方の男たちのタッグプロジェクトなわけなのである。しかもその建築を請け負った大宜味大工、金城組の棟梁も20代という若さだったとか。




-1-送付用-150x112.jpg)










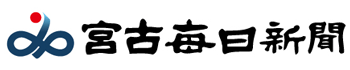


-1-150x112.jpg)
