ザトウクジラ、国内4海域を1集団が利用 保全に向け貴重な発見 沖縄美ら島財団など
- 2022/12/12
- 社会

沖縄美ら島財団(本部町)やエバーラスティング・ネイチャー(東京都小笠原村)、奄美クジラ・イルカ協会(鹿児島県奄美市)など6つの団体によるザトウクジラについての共同研究で、沖縄、小笠原、奄美、北海道の国内4海域にかけて、同一のザトウクジラ集団が来遊していることが判明した。さらにその集団内に2つの小グループが存在する可能性も示唆された。美ら島財団は「絶滅危惧集団とされている国内のザトウクジラの保全に向けて大変貴重な発見」と位置付けている。
今回の研究成果については、オンライン学術誌「PLOS ONE」に掲載された。
不明だった来遊海域間の関係性
夏季は高緯度海域で摂食を行い、冬季には低緯度海域で繁殖(交尾、出産、子育て)をするザトウクジラ。西部北太平洋海域では、ロシア周辺が摂食海域、沖縄、奄美、小笠原、フィリピンマリアナ諸島周辺が繁殖海域、北海道などが回遊途中海域として知られている。
沖縄美ら島財団では、繁殖海域の一つである沖縄周辺海域で1991年から30年以上にわたり来遊状況などの野外調査を実施。これまでロシアー沖縄間で計69個体、フィリピンー沖縄間で計100個体の同一個体を確認してきた。一方で、来遊海域間の交流や関係性については不明な点が多く残されていたという。
3,532頭分の写真を自動照合

今回の研究では、1989~2020年に撮影した3,532頭分のザトウクジラの尾びれ写真(模様や形状で個体識別が可能)を自動照合した結果、沖縄ー北海道間で3頭、沖縄ー小笠原間で225頭、沖縄ー奄美間で222頭、小笠原ー奄美間で36頭の一致個体が見つかった。
これらの一致個体数を基に海域間の交流指数や各海域の回帰指数を算出したところ、国内の4海域を一つの共通集団が利用していることが判明。ただ海域間で交流頻度は異なるため、フィリピン海の太平洋側(小笠原からマリアナ諸島)と東シナ海側(奄美、沖縄、フィリピン)をより頻繁に利用する2つの小グループが存在する可能性も示唆された。
冬場の沖縄観光を支える
今後に向けては、西部太平洋全体の個体数や来遊海域間の関係などの把握を目的に、国内外の各組織との共同研究を予定しているという。
ザトウクジラについては、国内各地でホエールウォッチングの対象として注目されており、沖縄県内においても参入事業者が増加傾向にある。冬場の観光産業を支える貴重な観光資源として利用されており、美ら島財団は「これらの研究成果は、観光産業のおいて今後も重要な位置を占めるザトウクジラの資源管理や保全活動に役立つと考えられます」と説明している。





















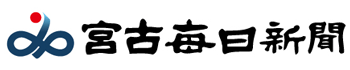


-1-150x112.jpg)
