「中間報告書」が指摘した首里城警備体制の杜撰
- 2020/9/18
- 社会
警備員に夜間火災の訓練が不足 実質的な初期消火はなかった
「中間報告書」は県、管理者、警備会社に忖度せず、警備体制の在り方に厳しい注文を付けている。
〈初期消火活動の着手が遅れ、正殿内の消火器や屋内消火栓の利用もできなかった。また、夜間の火災を想定した教育訓練が不足しており、警備員間の役割分担、警備員と監視員との連携や情報共有も不十分であり、実質的な初期消火活動には至らなかった。
さらに、消防局への情報の伝達及び消防局との連携が不十分であり、消防隊の到着時点で城郭内に入る通路の車両進入止や複数の門扉(ゲートボックス近くの管理用ゲートを除く)が施錠されたままで消防活動の障害となった〉(「第2−5(2)初期段階の対応における問題点」)
いかにリスクマネジメントが共有されていなかったことか。管理者の沖縄美ら島財団が警備員に夜間消火訓練を施してなかったことや、現場間の連携不足などが明らかになった。訓練について、私が11月段階で首里城管理事務所に問い合わせた際には「職員に昼間、実施しています」という回答だった。「警備員には?」と問うと「職員です」と答えるのみだった。
一説には、城郭内の非正規2人の警備員は、人感センサーが発報しても、2人態勢で出動しなかったという。その理由が「仮眠を取らせていたから起こさなかった」というものだ。これが事実なら、最終報告書ではその真偽も明らかにしてほしい。
首里城が「県民のシンボル」「心の拠り所」「沖縄のアイデンティティー」であり、観光立県の目玉であるなら、人も予算も掛けるべきだろう。設置者の県、管理者の沖縄美ら島財団、警備会社は、中間報告書を重く受け止めるべきである。















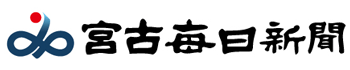


-1-150x112.jpg)
