「農業×観光」新たな6次産業の形 Sunset Farm Okinawa
- 2020/9/9
- 経済
車を停め電照菊を撮る女性
2014年、社員10人とその家族でハワイに旅行した。たまたま訪れたコーヒー農園やパイン畑。研修のつもりは全くなく、ただ、楽しむために行った。
「ビックリしたんですよ。農業が全部観光とくっ付いていました。コーヒー農園だったらコーヒーを直接お客さんに売っているし、焙煎体験もさせていました。パイン畑には加工品はもちろんグッズもいっぱい。うちも何かやろうと」
それから数年間、何をすべきか考えていた。何か別の作物を増やすべきか、加工品を作るべきか。ちょうど時は2016年。菊の輸入品が市場を席巻し、沖縄県産菊のブランド価値が落ちていた時でもあった。
「菊栽培の本業で赤字ぶっこいてたので、新しい取り組みできる余裕がなかったんですよ」
そんなある日だった。まだ外は暗い朝の4時、畑の見回りに出ていた池原さんは、転んで側溝に落ち、頭を切る大けがをしてしまった。血だらけだった。幸いにも日帰りの治療で済むものの、これがくしくも自分自身の背中を押すタイミングを作り出していた。
「いつ死ぬか分からないからやろう」
ふと思い出したのは、自分たちが電球の交換をしている時に、わざわざ車を停めて写真を撮っている女性たちだった。「もしかしたら、別のことに手を伸ばさないでも、そのまま電照菊でいけるんじゃないかと」。
病院から帰ったその日に、大手旅行会社に電話した。
「沖縄の電照菊って、観光コンテンツにしたら面白くないですか?」
とにかくたまたま電話を取った社員にそう伝えてみた。1日が経ち、2日が経ち、1週間が経っていた。やっぱり需要は無かったのかな、と思った。
そんな矢先だった。知らない番号からの着信を受けると、旅行会社の部長からだった。
「電照菊農家ご自身がこのようなことを考えているとは思いませんでした。すぐに会いたいです」
観光業界も沖縄の夜のエンターテイメントの掘り起こしに躍起だったのだ。

3代続く菊への思い
菊作りの歴史は、池原さんの2代前、祖父・昌徳さんの時代に遡る。
読谷村長でもあった昌徳さんが政界から退いた後、趣味の一環で育てていた菊の花。趣味といえどもJAに出荷するほどの腕前だったという。
当時東京に住んでいた父・昌富さんがたまたま菊栽培を手伝い、JAに出荷しに行った際、伝票に書いていた内容が驚きだった。
「1ケース1万円」
200本ほどで1ケースが埋まっていた。東京で佐川急便の運転手をしていたが、尊敬していた上司の死で新しいチャンスを探していた矢先。昌富さんは「沖縄の電照菊はどうやらすごいことになりそうだ」と沖縄に戻る決意をした。
1980年代は“第一次電照菊バブル”が起きていたという。
「うちの親父みたいな第一世代の人は、家を建てたら『菊御殿』と言われていたようです」
幼き池原さんは、父の農園が徐々に拡大されていく様を見ていた。
「最初はすごく小さい小屋があったんですけど、どんどん海賊のような見た目のいかつい男たちが増えてきて。彼らが従業員だったんですよ」
毎月のように、初めて見る男たちが増えていった。
「その“海賊”のお兄さんは、今はみんな独立して社長をしています」



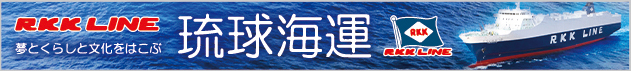




ー1-150x112.jpg)









-1-150x112.jpg)
