【復帰50年】「劇場が街を作り出した」戦後~復帰の大衆娯楽と沖縄
- 2022/4/26
- エンタメ・スポーツ

戦後から本土復帰を経て現在まで、激動の50年を経てきた沖縄。政治や経済の分野で大きな変化が訪れたのは言わずもがなだが、市民生活に欠かすことができない「娯楽」もまた、目まぐるしく変化してきたし、今現在も変化し続けている。
NPO法人「シネマラボ突貫小僧」代表で『沖縄まぼろし映画館』著者(當間早志共著)でもある平良竜次さんは「戦後沖縄の街、特に那覇は劇場が出来た場所に人が集まったことでできました。劇場が街を作り出したと言っても過言ではないと思います」と語る。
そこで、戦後から復帰にかけての大衆娯楽の場であった「劇場」の推移にフォーカスしながら、沖縄のあゆみと本土復帰について平良さんと考えてみたい。
アーティストたちが公務員だった
沖縄戦後の最も有名な劇場といえば、国際通りの名称の元となった「アーニーパイル国際劇場」だ。米軍政府の正式な認可のもとで開館した沖縄では戦後初の常設映画館で、現在の牧志にある那覇市ぶんかテンブス館付近にあった。
「劇場のオーナーは戦後活躍していた実業家の高良一で、当時は軍用地だった牧志地区にあたりをつけて劇場を建てました。当時闇市として賑わっていたのは今の壺屋から開南にかけての一帯だったのですが、劇場ができたことで人が集い、やがて牧志が繁華街になった。それが今の国際通りにつながっているんですね」(平良さん)
終戦直後でまだまだ殺伐としていた時期、本格的な映画上映が始まるまでは市民にとってほとんど唯一と言っていい娯楽は芝居だった。
民衆慰問のために沖縄芝居の役者が集められて、沖縄本島を3地区に分けて巡回する移動劇団(松・竹・梅劇団)がつくられた。これは沖縄民政府が認可したもので給与も支払っており、アーティストたちが言わば“公務員”として各地で公営劇団として公演していたということだ。
「北部を回った竹劇団に所属していた方に聞いたのですが、巡回していた当時、それなりの大きさの劇場があるのは名護ぐらいで、それ以外の地域では電気も通っていない所も多く、そういったところではかがり火をたいてお芝居をしていたといいます」と平良さん。「役者は集まった地域住民たちからものすごく感謝されて、お礼にお米をもらえたらしいんです。当時はまだ食料不足だったため『北部を回る劇団は良い思いができる』と、他の劇団から羨ましがられていたという逸話も残ってます」

南洋、大阪、奄美…多様な芝居業界
先の公営劇団が自由業となった1948年ごろから、県内では多くの劇団が新設され、県外に疎開していた沖縄関係者の劇団も本島に乗り込んできた。平良進さんや平良とみさんが所属していた「翁長小次郎一座」は戦前、サイパンで結成、巡業していた劇団で、戦後は宮古島や石垣島で長期公演を行っていた。
「翁長一座のようにサイパンから離島、そして本島に乗り込んでくるという流れもありましたし、大宜見小太郎さんのように、大阪で沖縄芸能の舞台を打っていた方たちもいました。さらに、沖縄とは違った本土仕込みの華麗な芸能を披露する奄美の劇団も那覇で公演を行うなど、この頃の芝居業界はかなり多様な状況だったと想像しますね」(平良さん)








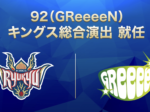






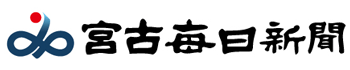


-1-150x112.jpg)
