【歴代知事③】「ウチナーンチュの特色」説いた沖縄保守の”ドン” 3代目・西銘順治
- 2022/9/3
- 社会

「いくらヤマトンチュになろうと思っても、なりきれないというウチナーンチュとしての特色がある」
3代目知事として歴代最長の3期12年(1978年12月10日〜1990年12月9日)、沖縄のリーダーを務めた西銘順治が発した有名な言葉だ。
沖縄の本土復帰後、初の保守県政を築き、予算獲得に向けて「中央との太いパイプ」を構築し道路や港湾など様々な社会資本を整備。国際会議の誘致を見据えた沖縄コンベンションセンターの建設など、現在の沖縄の経済発展に繋がる基盤を造った。冒頭の言葉に凝縮されるように沖縄のアイデンティティーにこだわり、「世界のウチナーンチュ大会」の創設や県立芸術大学の開学などを通した「人づくり」にも邁進。那覇市長や衆議員議員も歴任して沖縄保守政界の”ドン”と称されたが、「熟慮断行」の県政運営や厚い人情で保守、革新を問わず幅広い人脈を築いた。
パラオで培った「何くそ」精神
1921年11月5日、与那国村租納(現与那国町)で生まれた(※参考「西銘順治日記 戦後政治を生きて」琉球新報社編)。石垣尋常高等小学校5年の時、パラオで鰹節工場を建てた父・順石に呼び寄せられ、パラオ尋常高等小学校に転校する。
西銘はこの時のことを「いきなり南洋パラオに行って、植民地教育の中に放り込まれた。周囲はみんな南洋庁の官僚、高官、事業家など民間の金持ちの子弟の間に挟まって、大変窮屈な思いをした」と振り返っている。当時、パラオに沖縄の人は少なく、現地の日本人らから蔑視やイジメがあったという。それでも反骨精神を胸に勉学に励み、6年生の最後には卒業生総代に選ばれた。
後の1970年、自民党公認で衆議院議員選挙に出馬した際、「沖縄の歴史は琉球処分から苦難の連続だった。何くそ、ヤマトンチュに負けてたまるかとの気概を百万県民が持った時、はじめて日本一の県になると思う」と街宣で聴衆に呼び掛けた西銘。
西銘の長男で、知事当選後に秘書を務めた元参議院議員の西銘順志郎さん(72)は、パラオで過ごした子ども時代の話をする父の姿をよく覚えている。
「親父はパラオで生活してる時、ヤマトンチュとの賃金格差とか差別を肌で感じ取ってるんだよね。それで『成績でヤマトンチュに負けてなるか』と。それまで卒業式の総代はずっとヤマトンチュが務めていたらしいけど、自分がウチナンチュで初めて総代として卒業証書をもらったんだっていつも自慢してた。その時に培われた精神はずっと心の中に残ってたんだと思いますよ」

小学校卒業と同時に沖縄に戻った西銘は県立第二中学校を経て、1940年に茨城県の旧制水戸高校に進学、43年には東京大学法学部政治学科に入学した。県立第二中の時の物理の教師は、68年に沖縄初の首席公選で”子弟対決”を演じることになる屋良朝苗(復帰後の初代県知事)だった。
社大党結党に関わる 「政治力の結集」訴え保守へ転身
戦時中は海軍に所属し、インドネシアで終戦を迎えた。東大に復学、卒業後に帰郷し、1949年に社長として「沖縄ヘラルド」新聞を創刊。米軍の占領政策で住民の人権がおざなりにされる中、沖縄の日本復帰論を展開し、米軍批判を強めた。翌50年には社大党の結党に参加し、沖縄が米国施政下に置かれることになる52年のサンフランシスコ平和条約の発効が迫る中、沖縄全土を行脚して日本復帰の署名運動も行った。
54年の立法院議員選挙において社大党公認で初当選し、政界へ。西銘はこの頃、米国軍政下の厳しい状況を打破するため、「新たな政治力の結集」や「政党再選」を訴えるようになる。1955年11月2日にあった社大党の中央執行委員会では、こう述べた。
「首席公選をはじめ自治権の拡大を図るために、党は社会主義的色彩を払拭し国民政党に脱皮する必要がある。その上で、民主党や無所属議員を含め政治力を結集し、新党を結成すべきだ」
しかし主張は受け入れられず、党への不信感を募らせ、早くも政界引退を考えるようになる。8日後の11月10日、党の中心人物の1人だった安里積千代(後の衆議院議員)と面会した際のことを日記に残す。「政治力結集の経緯と真意を伝える。新党構想から手を引くことを声明する。桜坂で飲み直す。轟沈。寂しい。無上に人間の信じられない夜だった。社大党の性格がつくづく嫌になる」
1956年の立法院議員選挙で落選すると、実業家の道を志す。琉球石油社長の稲嶺一郎(後の参議院議員)や那覇市長の当間重剛らの協力もあり、同年に琉球造船の専務に就いた。当間が行政主席に就くと琉球政府の経済局長を務め、その後に保守政治家へ転身。60年の沖縄自由民主党結成を中心人物の1人として実現し、61年12月の那覇市長選では自民党公認で初当選。史上最年少の40歳で市長に就いた。
沖縄戦後初の衆議院議員の一人に

1970年11月16日(沖縄県公文書館所蔵)
西銘が社大党に所属していた頃から必要性を訴えてきた首席公選が1968年11月、ついに実現する。日米両政府の支援を受けた西銘は自民党公認で出馬したが、県立第二中時代の恩師で、革新統一候補の屋良朝苗に3万票以上の差を付けられて落選。それでも2年後に沖縄にとって戦後初の国政選挙となった衆議院議員選挙でトップ当選を果たした。
田中角栄らに薫陶を受け、沖縄開発庁政務次官や経済企画政務次官を歴任し、中央で多くの人脈をつくっていった西銘。屋良県政のほか、自身と同じ社大党結党メンバーの1人で屋良から革新県政を引き継いだ2代目知事・平良幸市の県政下においても、保革の壁を越え、知事と一致協力して沖縄のために予算獲得に動いていたという。1978年7月、平良が1期目途中で病に倒れた時のことを書籍「土着の人」(平良幸市回想録刊行委員会編)で振り返っている。
「国立病院に平良さんを訪ねたが、言葉も出ず涙が出るばかりのさびしいお顔を拝見して、いい知れぬ感嘆におそわれ自分も涙を流してしまったものである」。さらに平良のことを「高潔な政治家」と評した上で「非常に政治感覚の鋭い持ち主であり、温厚篤実な方で、いろいろな点で御指導を受けた愛すべき大先輩であった」と記し、袂を分かった後も親しい間柄だったことをうかがわせた。



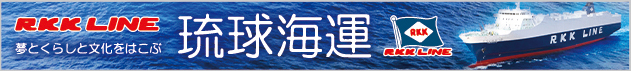

-150x112.jpg)












-1-150x112.jpg)
