美ら海だけじゃない、本部町の「水スポット」を楽しむ
- 2022/3/24
- 社会

本土の人に「ホンブ?」とよく間違われていた「本部(モトブ)町」。
しかし今では美ら海水族館を含む海洋博国立公園、備瀬のフクギ並木や瀬底島の人気も相まって沖縄観光産業を牽引する町の一つだ。本部町には、水族館の他にも「水」に関する興味深いスポットがいくつもあるので今回はそちらを紹介しよう。
本部はもともと「今帰仁間切」の一部だったが、1666年に間切西側を中心に分離され「伊野波間切」が新設された。翌年に「本部間切」と名称を変え、明治期に「本部村」となった。1940年には本部町に昇格するも、沖縄戦の影響により1947年町北部が北本部村として分離され、本土復帰直前に再編入が行われ現本部町となった。
現在も海洋博公園近くに沖縄戦の名残である上本部飛行場の滑走路跡がある。
世界に2つしかないレアな川
名護から本部半島沿いに車を走らせると、名護市と本部町の境界付近に長さ約300mほどの短い川「塩川」を見ることができる。この川は海岸近くに湧き出た水が海まで流れ込む水流なのだが、不思議なことに塩川の湧き水には塩分が含まれており、昔から方言で「スガー」と呼ばれる塩の川なのだ。
塩分が含まれる川は世界的にも非常に珍しく、ここ塩川とプエルトリコにもう1つが確認されているだけだという。沖縄が本土復帰した1972年に国の天然記念物に指定された。
未だ詳しいメカニズムは解明されていないようだが、海水の潮位と湧き水の水量に一定の関係性が見られること、また湧き水の水量と塩分濃度にも一定の関係性が見られることから、海水がなんらかの形で湧き水に流れ込んでいるのではないかと考えられるようだ。
さらにこうした特殊な自然環境のため、塩川には日本で唯一「シオカワモッカ」という藻が生息する場所となっている。だが塩川のすぐ裏手は広大な琉球石灰岩採石場となっており、乱開発による湧き水の水質汚染が懸念されている。
我々ウチナーンチュも知らぬ間に開発へ加担している側になっているかもしれないが、しっかり自分ごととして考えていきたい。
















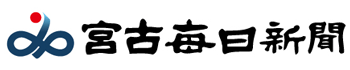


-1-150x112.jpg)
