小さな島から見えてくる、どの土地にも“地続き”なこと 『水納島再訪』橋本倫史さんインタビュー
- 2022/3/3
- 社会

コロナ禍でより際立った「境界線」
―本文中で自身のことを「余所者(よそもの)」と表現していたことにも象徴されていますが、離島と本島、沖縄と日本、という色んな局面での“境界線”が対照的に浮かび上がっていたように思います。
「余所者というのは水納島に限らず、どの場所で取材している時でもそんな気持ちでいます。
しかも今このコロナ禍という状況で、県境とか県をまたぐ『移動』という言葉がネガティブな響きになった時に、みんなが自分の住んでる地域だけに目を向けるようになってしまう気配を感じていて。その中でもともと自分の中にあった境界線の意識が際立ってきたんだと思います。
沖縄だけでなくどこに行ってもそうなのですが、何日かそこで過ごしているうちに、ともすれば自分も“その土地の人間”だと錯覚してしまいがちだと思うんです。でも、そんな気になってちゃ駄目だなと。
自分は余所者だという感覚を持っておかないと、バランスがおかしくなる。というのも、ある土地が抱える問題について、そこに暮らす人だけではなく、その外側に暮らす人も関心を持つべきだと思うんです。『これは水納島だけの問題じゃないですからね』と言うためにも、境界線ということは意識的に、自分でも自制するように話を聞くようにしていました」

―橋本さんは沖縄もそうですが他にも色んな場所を旅して文章を書かれています。さっきも出た“余所者”としてある場所を眼差す時に、どのような考え方でアプローチしていますか。
「僕は生まれが広島ですけれど、地元だからと言って自分の街のことを隅々まで知っているわけではありません。言ってみれば『その場所にいるひとり』でしかなくて、その中でどういう態度でいるかということだと思います。
その意味では、たとえば広島のことについて『地元の人間としてこう思う』という物言いはとてもできないなと思うんです。そういう主語が大きい言葉より、『私としてはこうです』という言葉を積み重ねた方が、きちんと言葉を交わせる気がするんです。その視点でいたいというか。
僕はノンフィクションやルポルタージュを書いていて、それはつまり、自分以外の誰かや、普段の生活圏とは異なる土地を取材して原稿を書く仕事です。だから、対象を完全にわかることなんて、永遠にないと思うんです。だからと言って、文章として書くこと、何かを残すことを諦めてしまうわけにもいかない。
当事者にはなり得ない自分に『どういう手の伸ばし方があるのか』ということはずっと考えているし、大事なことだと思っています」




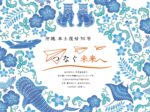












-1-150x112.jpg)
