首里城は誰にとってのシンボルなのか 再建を考える(下)
- 2021/1/8
- 社会
首里城の火災から1年余りが経ち、各方面からの視点で再建を巡る議論がされている。前回話を聞いた沖縄国際大学の桃原一彦教授は、火災から3ヶ月が経った昨年2月にゼミの在学生と卒業生を交えて「首里城についてどう思うか」をテーマに、沖縄の過去の映像記録なども参考にしながらディスカッションを行った。そこでの議論も踏まえて、ディスカッションに参加した卒業生の仲里淳さん(40)、屋嘉部大介さん(36)の2人に首里城再建について県民として感じることや考えることを改めて語ってもらった。
【関連記事】首里城は誰にとってのシンボルなのか 再建を考える(上)

本当に「心のよりどころ」なのか?
仲里さんは火災発生当時、出張で東京にいた。全国ニュースでトップ扱いの報道を見て知ったという。その時の率直な感想は「ああ、燃えてるなあ、と。それ以上はこれといって感じたことはなかったように思う」。首里寒川に生まれ、その後も那覇市内で育ち、首里城の存在は物理的には近くにあったものの、報道などで「心のよりどころ」というニュアンスが強調されていることにはかなりの違和感を覚えた。
「正直言って“よりどころ”にはしてないし、『本当にそう思ってる?』という疑問の方が先に湧いてきた。テレビで燃えた首里城を見ながら泣いている人たちも映っていたが、それも『本当に?』という感覚が大きい。
もちろん全否定するわけでもない。ただ例えば、昔から続いている行事ごとに則って、頻繁に首里城で祈りを捧げているような人が涙するということであれば理解できるが、あの時のような『皆が悲しまないといけない』という空気感にはある種の違和感も感じた。
小さいころに守礼門にちょくちょく行ってたので、そちらが仮に被害を受けていたら、もしかするともう少し思うことはあったかもしれない」
出張先から沖縄に戻ると、既に再建・復元についての動きが出始めていて、対応のあまりの速さには危うさも感じた。「首里城再建という動きに、沖縄のアイデンティティみたいなものを統合・集約しようとする過程を見ているかのようで、非常に居心地が悪かった」




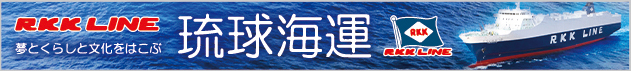














-1-150x112.jpg)
