首里城は誰にとってのシンボルなのか 再建を考える(上)
- 2021/1/4
- 社会

2019年10月末、火災の発生で正殿含めて7棟の建物が焼失した首里城。首里の未明の空を赤くするほどの激しい炎上から1年余りが経過した。火災の直後から県内外で再建の動きが起こり、加速度的に機運が高まった。発生からある程度時間が経過してさまざまな視点で議論が進められている現在、沖縄県民として首里城をどのように捉えてきたか、その歴史と文化を踏まえて再建についてどう考えていくべきか、沖縄国際大学で教鞭を執る桃原一彦教授(社会学)に話を聞いた。
首里城への違和感と距離感
―火災発生当時、首里城焼失についてどう感じましたか。
「火災発生の時間帯は確か仕事で起きていた。自宅が石嶺なので、消防車が騒がしいなとは思っていたが、翌日のニュースでちゃんと知った。各メディアで大々的に報道されていて、大きな事件だなと思った一方でうまく言葉にできない、ピンとこない部分もあった。
火災から3週間後くらいのタイミングで、ここ3~4年ほど継続している社会調査で兵庫県尼崎のウチナーンチュコミュニティを訪れたのだけれど、そこの人たちも皆ショックを受けていた。沖縄の地元の人たちが心を痛めているのではないかと心配して募金活動をしたり、県人会でも何か動こうという話もあって、再建に向けての熱量を感じた。
その中には宮古出身の人もいて、首里や首里城に対しては特別な思いはないけど、やっぱり衝撃は受けたと話していたのも印象的で、地元の沖縄から離れているからこそ存在が大きいというのはあるのかもしれない。その意味では“沖縄のシンボル”みたいな捉えられ方はやっぱりされてるんだなと」
―首里城そのものに対して、これまでどのように考え、向き合ってきましたか。
「火災から少し時間が経って落ち着いた時に、僕のゼミの在学生と卒業生で首里城についてどう感じているか、どんな思いがあるかという議論をした。
何となく予想はしていたが、『生まれてから1回も首里城行ったことない』という声もある程度あった。在学生は大体20歳前後で、卒業生は30代後半くらいまでの世代。なるほど、確かになという感覚はあった。かく言う僕も50年生きてきて、実は有料区域には1度しか入場したことない。
僕は大学は沖国で、大学院は東京に進学してて、東京にいるタイミングで92年に首里城公園が開園した。首里にルーツもなく首里城に対する思いも特になくて、再建していたこともその時に知ったくらいだった。里帰りした時に1度中に入って、それきり。
だから、火災で焼失したといっても『あまりピンとこない』という学生たちの感覚も何となく分かる気がした。

沖縄の戦後復興という意味合いで首里城が再建されたのはとても重要なことだとは思うし、その過程での職人さんたちの技術や苦労には最大限の敬意を払う。しかし、その一方で『これが琉球だ』『これが沖縄だ』ということを手放しで言えるという感覚は正直ない。それはおそらく自分が沖縄で生きてきた歴史と首里城の存在とが上手くつながっていないからだと思う。
いわゆる観光ブームになって以降は輪を掛けて観光施設的イメージが強くなり、違和感や距離感が出てしまった。特に有料区間だと、ただでさえ年収や所得の低い沖縄の地元の人はますます行かないだろうなと。学生たちも同じような意見だった」



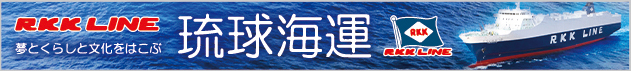













-1-150x112.jpg)
