【歴代知事①】刻まれた眉間の「縦じわ」 初代沖縄県知事・屋良朝苗の苦悩とは 復帰50年
- 2022/5/23
- 政治

5月15日に東京と沖縄をオンラインで繋いで開かれた「沖縄復帰50周年記念式典」。壇上の大画面に映し出された沖縄の歩みを振り返るオープニング映像に、ちょうど50年前の1972年5月15日に那覇市民会館で開かれた沖縄復帰記念式典の様子が映し出された。
「沖縄県民のこれまでの要望と心情に照らして、復帰の内容を見ますと、私共の切なる熱願が必ずしも十分に入れられたとはいえないことも事実であります。そこには米軍基地の対応の問題をはじめ、内蔵するいろいろな問題が存在し、これらを持ち込んでの復帰になったわけであります。これからもなお厳しさは続き、新しい困難に直面するかもしれません」
苦悩の象徴とされた眉間の「縦じわ」を一層深くし、原稿に目を落としながらマイクの前で式辞を述べていたのは、復帰後、初代県知事となった屋良朝苗。当時69歳。復帰を祝う場で、腹の底から発する言葉の歯切れは良いものの、その声には怒気や無念さが入り混じっていた。

1945年の終戦から27年間続いた「アメリカ世(ゆー)」から「ヤマト世(ゆー)」へ。「祖国復帰運動」を牽引し、歴史的な世替わりの瞬間に沖縄のリーダーを務めた屋良の生涯とは。
校舎復興のため全国行脚 教育は「一条の光」
1902年12月13日、屋良は4男1女の四男として読谷村瀬名波で生まれた。広島高等師範学校を卒業後、沖縄県立第一高等女学校や台北師範学校などで教鞭を取り、終戦後の1946年に沖縄に戻った。

サンフランシスコ講和条約が発効され、沖縄が日本から切り離された1952年、教員を束ねる教職員会会長に就任する。沖縄戦で荒廃した沖縄の復興に向け、教育の再興と日本への復帰を目指した屋良は、以下のような言葉を残している。
「沖縄の将来は霧やモヤに包まれている。その中を県民が向かうべき方向を誤らずに進んでいくためにはやはり闇を貫き前途を照らす一条の光が必要である。その一条の光こそ、まさに教育である」
1953年には戦災を受けた校舎の復興に必要な募金を呼び掛ける全国行脚を慣行。日本政府や国会に沖縄の窮状を訴えた。
復帰運動の中心に 持ち合わせた二面性
米兵によって少女が殺害された1955年の「由美子ちゃん事件」や、軍用地地料一括支払い反対などを拒否する1956年の「プライス勧告」に端を発した「島ぐるみ闘争」など、様々な不条理に晒される中、民衆の米国統治に対する不満が膨れ上がっていった50年代。日本復帰を求める声や運動も日に日に強まっていく。

運動を牽引した教員たちの長である教職員会会長の屋良は、教育問題にとどまらず、復帰運動の中心も担った。沖縄県祖国復帰協議会が発足した1960年に屋良の秘書となった石川元平さん(84)は、当時の様子をこう振り返る。
「何かあればぱっと外出できるように、会長室の壁には背広と帽子がいつも掛けてあって、常時専属の運転手が待機していた。仕事に厳格で近寄り難く、『屋良天皇』という呼び名もあった」。ただ、違う一面もあったようだ。石川さんが続ける。
「若い連中でお酒を飲んでいて、『今日は会長に文句の一つでも言ってやろう』ってなったことがあるんだよね。あの頃は僕が1番若かった。それで会長の所に行ったら『君たちにはいつも苦労を掛けてすまんな』と言うんですよ。それには救われた。そんな二面性も持っていましたね」



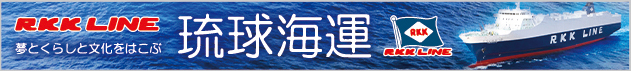
-150x112.jpg)













-1-150x112.jpg)
