- Home
- 暮らし・教育・子育て
- 設備は不十分、方法も手探りで教員は疲弊 オンライン授業の困難さとは
設備は不十分、方法も手探りで教員は疲弊 オンライン授業の困難さとは
- 2021/11/9
- 暮らし・教育・子育て

「オンライン授業をするための十分な設備や環境などのインフラが、うちの学校には整っていませんでした。何とか間に合わせて乗り切りましたが、かなりの疲労感を覚えました」
こう振り返るのは沖縄本島中南部の公立小学校に勤める男性教諭だ。新型コロナウイルスの感染拡大で緊急事態宣言が発出されていた際、この男性教員の小学校では低学年向けのオンライン授業を1週間実施したという。小学校では高学年向けならば画面越しでの授業はある程度成り立つが、低学年だと機器の扱いにも不慣れな上、集中力の持続も難しい。さらに、教師・学校側の準備や運営もまだまだ手探り状態だ。
文部科学省は2019年から「GIGAスクール構想」として小中学生への端末1人1台整備などを含めた政策を推し進めているが、課題は多い。コロナ禍以前から多忙だった教育現場の負担はオンライン対応でさらに増し、教員の疲弊も大きいのが現状だ。
アルファベットも習ってないのに…
男性教諭は「WEB会議アプリのZoomを立ち上げるためのPCは1学年に1台ずつです」と説明する。そうすると、必然的にオンライン授業では1学年の児童全員を相手にすることになる。100人を超える児童たちを相手に画面越しでまともな授業を成立させることの困難さは、想像に難くない。
また、低学年の児童の中には、お菓子を食べていたり、寝っ転がりながら受ける子どもたちも画面にちらほら見えて「双方向型の授業として成立させるのは到底無理」な状態だった。加えて大変だったのは、パスワードの入力だ。「1年生や2年生だと、タイピングどころかアルファベットも満足に習っていないので、ログインの仕方を教えることにもかなりの労力が要るんです」。
それゆえ、文字としてではなく「同じ形のものをタッチして」といった説明で何とか教え込み、セキュリティ上の問題が多少あるもののパワスワードの文字には大文字を入れ込まないようにするなど、さまざまな“苦肉の策”を講じながら懸命に対応したという。

学校間でのデジタル設備の落差
新型コロナの影響による休校措置期間中、本島中南部のとある学校のオンライン授業への取り組みの様子が県内の各メディアで取り上げられた。報じられた学校はコロナ禍になる前からICT教育の先進校で、デジタル端末を使用した双方向型の授業をしっかりできる充実した環境が備えられていた。
しかし上述の通り、実際にはクラス単位でのオンライン授業を実施できるだけの数のPCもなく、さらに教員の中にもZoomの使い方を知らない人も少なからずいたというのが現実で、全ての学校に十分な設備があるわけではなく、報道された学校との“落差”は大きかった。















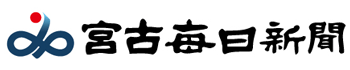


-1-150x112.jpg)
