- Home
- 宮城亜茶子の生活と意見
- 連載小説・宮城亜茶子の生活と意見 第九回
連載小説・宮城亜茶子の生活と意見 第九回
- 2021/4/18
- 宮城亜茶子の生活と意見

日曜日、亜茶子はGMW号に乗って泉崎にある県立図書館に向かった。前日の夜、久しぶりに体重計に乗ったら七十キロが目前に迫っていて、衝撃と戦慄から〈明日はとにかく外出しよう!〉と決めたのだった。ここ数ヶ月は運動不足が続いていたことに加えて、深夜に食べるポテチやカップラーメンも巨大化の要因だった。
久茂地川沿いを走りながら、図書館が与儀にあった頃は宮古のおじぃとよく遊びに行ったことを思い出した。海人だったおじぃは寡黙な変わり者で、家族の中ではかなり浮いた存在だったが、亜茶子とはなぜか気が合って、開南の家から与儀に向かう散歩に何度も出かけたものだった。おじぃは宮古の方言で話す上に、歯の大半がなく、たまに口を開いても何を言っているのかほぼ聞き取れなかったが、自分のことを大切にしてくれていることは十分に理解できた。
おじぃとの思い出の中で一番記憶に残っているのは、図書館からの帰り、おじぃがパーラーで買ったポップコーンを地面に並べて鳩たちをおびき寄せ、近づいてきた一羽を両手でガバッと捕まえて顔の前に掲げたことだった。そのときは驚きのあまり「うわッ!」と叫んだだけだったが、今思えば、孫を楽しませようという不器用な愛情だったのだとわかる。確か、初めてデゴイチ(蒸気機関車)を見たのも、初めて石焼き芋を食べたのも、おじぃと一緒のときだった。
沖銀本店のある通りからパレット側へ渡り、琉球新報社の方へ向かった。横断歩道を渡ったあとは百メートルほど直進して、仲島の大石を過ぎて右手にある駐輪場にGMW号を停めた。初めて来る場所に少し緊張した亜茶子は、深呼吸をして気持ちを整えたあと、階段を上って図書館のあるカフーナ旭橋の中へ入った。
上りのエスカレーターに乗って、図書館の自動ドアを抜けると、白と茶色を基調とした未来的な空間が広がっていた。ゆっくり館内を歩いてみると、充実した展示のエリアや児童向けのエリアがあって、四階にはビジネスエリアや本土の新聞も読める情報エリア、サイレントルーム、交流室などがあった。のんびりと本を読んでいる人よりも集中して勉強している人の方が多く、その横や後ろを静かに歩きながら、亜茶子は自然と気が引き締まるのを感じた。
五階の郷土資料室で移民の展示資料を見たあと、過去の新聞記事が保存されてある場所に行き着いた。ずらりと並ぶ大型の本を眺めているうちに、ふと、自分が生まれた日の新聞が読んでみたくなった。「一九八六年 二月」と書かれた緑(新報)と青(タイムス)の二冊を抜き取って、両脇に抱えながらテーブル席に座り、十四日の紙面を開いてみた。
その日は金曜日で、異常乾燥注意報が発令されていて、「南のち北よりの風、曇り一時雨。気圧の谷の影響でぐずついた天気」と書かれてあった。自分の複雑な性格の原因をついに突き止めた気がして、亜茶子は小さな興奮を覚えて苦笑せずにはいられなかった。星座や血液型の占いはなんとなく信じられなかったが、生まれた日の天気と性格には深い関係があるように思われた。
新報とタイムスの両紙とも、一面では琉球バスと那覇交通(銀バス)の合併が白紙に戻ったこと、大統領選挙に伴って混乱するフィリピンに読谷のトリイ基地から特殊部隊が派遣されることを報じていた。社会面では、那覇市民憲章推進協議会の調査で結婚式や会議の時間を守る人が三割弱しかいないことが明らかになって、沖縄タイムを見直そうと県民に訴えかけている記事が印象に残った。
タイムスのスポーツ面には、PL学園から西武に入団した清原和博が期待の新人として紹介されていた。野球に詳しくない亜茶子でも、清原が何年か前に薬物事件で逮捕されたことは知っていて、プロ野球選手として華々しく活躍していただけに、その転落ぶりが一段と悲劇的に映ったことを覚えていた。人生、何が起こるかわからないな、と、亜茶子はしみじみ思った。
ページをめくっていると、久米仙酒造の広告に目が留まった。「ゆうわくシロー」と「よりどりミドリ」というやんちゃな名前の泡盛に「YOU JUST MAGIC」という謎のキャッチコピーがついていて、意味がわからなすぎて笑ってしまった。使われている写真も男女のベッドシーンを連想させるもので、今の社会的風潮からするとアウトだったが、ゆるい時代の空気が感じられて面白かった。
視線を上げて、目を通してきた記事に思いを馳せながら、亜茶子は世界について考えた。いつの時代も、社会は問題を抱えていて、それを解決しようとする人たちがいて、自分が想像もできないようなドラマがあったんだろうな、と思った。この先、人間の未来はどうなるのだろう・・・地球を離れて宇宙を目指そうとしている人類とは、一体なんなんだろう・・・
百年後の未来から今をふり返ったとき、自分が歴史的な転換点にいることは間違いなかった。新型コロナウィルスで世界は不安と恐怖の中にあって、オリンピックが開催されるのかどうかもまだわからなかった。ただ、何が起きようとも、結局は自分にできることしかできないので、とりあえずは体重を減らそう、と決めて、亜茶子は静かに本を閉じた。
(続く)



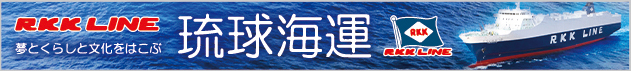














-1-150x112.jpg)
