- Home
- 宮城亜茶子の生活と意見
- 連載小説・宮城亜茶子の生活と意見 第六回
連載小説・宮城亜茶子の生活と意見 第六回
- 2021/3/13
- 宮城亜茶子の生活と意見

水曜日の夜、亜茶子は紫色の座布団の上に座って、録画していた大相撲を観ることにした。二十三歳の夏までは相撲に対して「喧嘩っ早いおデブちゃんたちのぶつかり合い」という偏見しか持っていなかったが、その年の秋場所で行司が着ている装束のデザインに興味を持ってから、好角家(相撲が好きな人)の道を歩むようになった。スーパーヘビー級の肉弾戦を見ていると、自分がスーパーモデル級に痩せているような気分になれるのも魅力の一つだった。
相撲を観はじめた当初は、漢字の音読みと訓読みが変則的に組み合わさった四股名(力士の名前)がなかなか覚えられなかった。あるとき、ふと思いついて、小学生のときにポケモンの名前を覚えたように「把瑠都(ばると)、臥牙丸(ががまる)、豊響(とよひびき)〜♪」とリズムに合わせて口ずさむようになった。そのうち、四股名と顔が合うようになり、今ではキラキラネームが増えた幕下力士のデータまで頭に入っている。
力士の取り口(相撲の取り方)や合い口(対戦相手との相性)がわかるようになると、相撲がさらに面白くなった。番付上位の力士が下位の力士に必ず勝つわけではなく、一瞬の隙や油断で形勢が逆転するところに勝負の醍醐味があった。体の大きな力士に挑む小兵力士(小柄な力士)を見ていると、グスク・トリオと戦っている自分の姿が重なって、番狂わせがある度に座布団をフリスビーのように投げ飛ばしたくなった。しかし、一度それをやってお気に入りのマグカップを割ってしまったので、今では代わりに亜茶子ダンスを踊ることにしている。
モンゴル勢を筆頭とする外国人力士の活躍を見ていると、亜茶子は心の底から「凄いな」と思う。海を渡って、難しい日本語を覚え、異文化とかわいがりの中で揉まれながら相撲を取り続ける苦労を思うと、万雷の拍手を送りたくなる。反対意見の方が多いだろうが、幕内優勝した外国人力士には日本国歌に続いて母国の国歌を流してもいいのではないか、と考えている。大相撲が時代の要所で形を変えてきた歴史を踏まえれば、これからも柔軟に変化していく余地は残っている。
いつだったか、亜茶子は相撲部屋の女将さんになった自分を妄想してみたことがあった。厳しい稽古をこなす力士と親方を支える忙しくもやりがいのある毎日。そんな中、息子が生まれ、相撲を取るようになり、中学二年の冬の朝、「母ちゃん、俺、力士になる」と告げられる。いつかこの日が来るとは思っていたが、ついに来てしまった。息子の意思を尊重しつつ「もう、お母さんじゃなくて“女将さん”って呼ばなくちゃいけなくなるのよ。それでもいいの?」と聞いてみる。うん。息子はしっかりと頷く。親子で過ごした楽しい思い出が走馬灯のように脳裏を駆け抜ける中、「わかりました」と受け入れ、深夜、誰もいない洗濯機の前で忍び泣く・・・・・・。ダメだ、私には耐えられない。亜茶子は頭を振って、これからも一人の好角家でいようと心に決めた。
ここ数年、亜茶子は馴染みの力士たちが次々と引退して寂しい思いをしている。飄々とした性格と多彩な技で観客を魅了した安美錦。小柄な体を最大限に活かして相手に真っ向勝負を挑み続けた尾車部屋の豪風と嘉風。大一番で星を落としてファンをがっかりさせながらも、十九年ぶりの日本人横綱に登りつめた稀勢の里。その中でも、琴奨菊がいなくなったことは大きなショックだった。気持ちが沈んでいたとき、琴バウアーと豪快な塩まき、そして見事ながぶり寄りにどれだけ励まされたかわからない。
十年以上観戦を続けていると、亜茶子は相撲から多くを学んでいることに気づかされる。その最たる例が「一日一番」だ。その日の一番(相撲)に集中するという意味で力士が頻繁に使うこの言葉を、いつからか、亜茶子はおまじないのように唱えるようになった。それまでは嫌なことがあるとしばらく引きずっていたが、「一日一番」と口にするようになってからは、勝っても負けても一礼して土俵を去る力士の姿が浮かんで、気持ちがうまく切り替えられるようになった。
結びの一番が終わっても、亜茶子は弓取式まで観ることにしている。器用に弓を振り回す力士を見ていると、小学生の頃にほうきを振り回して先生に叱られていた上間光之助を思い出す。あいつは今、何をしているのだろう。隅田川の夜景をバックに響くはね太鼓の音を聞きながら、亜茶子はぼんやりと、そんなことを考える。
(続く)



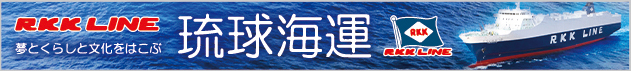














-1-150x112.jpg)
