書評『沖縄から貧困がなくならない本当の理由』(樋口耕太郎著、光文社新書)
- 2020/7/1
- 経済

沖縄の飲食店では大抵、塩、醤油、コーレーグース(泡盛漬け唐辛子)と並んで県外産の合成酢である「○○○○酢」が置いてある。戦後の食糧難時代ならともかく、21世紀を迎えて穀物酢や純米酢、玄米酢、さらにはワインビネガーやバルサミコ酢、リンゴ酢……とスーパーの店頭にいっぱい並んでいるのに、なぜ沖縄では○○○○酢が売れているのか。
同商品の成分表示を見ると、〈氷酢酸、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、食塩、砂糖〉とある。食塩、砂糖以外ほぼ工業原料の食品添加物ではないか。値段もタマノイリンゴ酢500ml=198円、ミツカン米酢同=236円(月間特売)、ミツカン穀物酢同=112円(果実酒フェア)に対し同酢は360ml=197円(月間特売)と、醸造酢系より割高なのだ(6月30日、ユニオン前島店調べ)。
かつてヒマラヤの塩にこだわり「くぇーぶー(グルメ)」を自任する方が、「ひーじゃー刺しを食べる時はまるこめ酢じゃないとね」と言っているのには驚いたことがある。「味は記憶」とも言われるが、ひーじゃーとて純米酢などで食べた方が美味しいはずなのだが。中には本マグロにも使う人がいて、あまりにもったいない。
なぜここまで愛用されるのか。東京から33年ぶりにUターンしてずっと腑に落ちなかった。しかし沖縄タイムス電子版の沖縄タイムス+プラスに掲載された「沖縄から貧困がなくならない本当の理由」を読んで、その謎が解けた。
樋口氏は合成酢の他に、レトルトカレー、カップ麵、ステーキソース、ランチョンミートなどを俎上に上げている。本書では【第2章 人間関係の経済】の中で「平凡な『定番』が異様に売れる市場」に収録され、ウチナーンチュが特定ブランドにこだわる理由をこう分析している。
〈売れる理由が、商品性でもない、価格でもない、地元産だからでもない、唯一残る可能性は、「いつも買っているから」「みんなが買っているから」つまり、商品を選んでいないからではないだろうか。そうでなければ、これらの商品が沖縄の定番になっていることの説明がつかないのだ〉
補足すると、これら商品はオリオンビールと違い、すべて県外、国外産であり、○○○○酢に至っては旧宗主国だったお隣県産で、実に95%を沖縄に出荷しているという。
事業再生を専業とする会社を経営し、沖縄大学で教鞭を執る樋口氏は、学生になぜ同酢を買い続けるのか聞いている。その答えがこうだ。
〈・親や周囲がそうしているから、それに反するものは買えない。商品の内容や良し悪しは、気にしないし、考えない
・昔から使っているものを選べば(人間関係で)失敗することがない。失敗すると人間関係に問題が生じる可能性もあるから〉
余談ながら「みださー(場を乱す人)」「マーメー(マメ、真面目)」という言葉も初めて知った。ここから見えてくるのは、商品ファーストではなく、周りとの関係性が優先され、自己主張の難しい「同調圧力」の強い社会での消費行動だ。そのような社会では現状維持ファーストで、変化やイノベーションは対極に位置する。
サンマリーナホテルを取得した縁から沖縄に住むようになった樋口氏は、さまざまな「ナイチャーの洗礼」を受ける。よかれと思って発した言葉が思わぬ人間関係の終焉を招いた逸話などは、駐在員や「移住組」には教訓になりそうだ。
樋口氏が主宰していた「次世代金融講座」の懇親会の出席確認メールになかなか返信しない行員がいたので、「長い間の知人であり、率直な会話ができる間柄」の先輩格の行員に相談した。
〈「彼らが忙しいのはわかるが、小さな連絡ごとに誠実に対応できなければ、大きな失敗につながるのではないか?」
私が彼から期待していた返答は、例えば、「ご迷惑をおかけして済みませんでした。今度機会がある時に、彼らときちんと話してみます」だったのだが、彼が私に返した言葉が想定外だった。
「いいえ、彼はいいやつなんですよ」(中略)
この、たった一言にはいくつかの効果がある。
第一に、後輩の問題行動を、黙認すること。
第二に、後輩の問題を、私の問題にすり替えること。
そして第三に、私が、いつの間にか加害者に、後輩が被害者になっていること。
一言でまとめれば、その先輩が、後輩行員に意見すること、(クラクションを鳴らすこと)を避けるため、私に圧力をかけたのだ。
彼にそんな自覚はない。沖縄社会の同調圧力は、このように、かなり微妙な空気感によって伝達される。
もちろん、沖縄社会は、この場合、何もしない後輩行員の見方である。
クラクションを鳴らした私は加害者であり、「冷たい人」というレッテルが貼られる。それを嫌って私が口をつぐめば、社会は現状維持されるのだ〉
樋口氏が数年の歳月を要して至った境地だ。
実は私自身、日常生活のさまざまな局面で、よかれと思い発した言葉で「みださー」になったことが幾度もある。遠縁の親戚が営む居酒屋でドラゴンフルーツが出されたので、「ワサビ醤油でもいけるね」と言ったところ、店主はとたんに怪訝な表情になった。単なるフルーツとして何もかけないで食べるのがいけないのか、と受け取ったのかもしれない。
またある時は、親族と行った別の店で「森伊蔵」を頼んだ時、なかなか出て来ない上、値段も把握していないので、アルバイトの女性に「もう○○分たってるんだよ」と言ったところ、アルバイトの女性は二度と座敷に姿を現さなくなった。親族から「もういいじゃないですか」とたしなめられ、ことごとく彼らの面子をつぶしたのだ。
樋口氏は【第2章 人間関係の経済】の「外食はまず『知人の店』」で、「味や値段より知り合いであることが優先される」と書いている。「ゆいまーる」の精神に基づくもので、私自身それ自体は悪いことだとは思わない。しかし、身内だからこそ耳の痛いことも言うべきで、それが店を成長させるためにもなるのではないか。
もっとも私がそう思うのは、私がいわゆるUターン組だからである。【第3章 沖縄は貧困に支えられている】の中の「戻ってきたウチナーンチュは危険人物?」を読むと、改めて自分の至らなさに気付かされる。
私など、特に本土でしかるべき実績を挙げて帰ってきた訳でもなく、組織に入って変革しようと意気込んでいる訳でもないのに、たまに微妙な距離や「サボタージュ」に近い扱いを受けることがある。そうだったのだ、存在そのものが危険だったのだ。
〈外で成功したウチナーンチュは「できるものいじめ」のターゲットになりやすく、沖縄に戻るとつぶされて居場所を失ってしまう。
沖縄県内で暮らすナイチャーも似たような立場に置かれることが多いが、所詮沖縄社会では「お客様」だ。「数年で本土に戻る」と思われているから、沖縄社会の「異物」ではあっても、それほど積極的に排除する必要がない。
しかし、帰ってきた(有能な)ウチナーンチュは別物だ。残りの一生を沖縄で暮らす可能性が高く、沖縄社会の安定した序列を崩して、本格的にパイを奪う存在なのだ。
だから帰ってきたウチナーンチュに対するサボタージュは、ナイチャーに対するよりもはるかに酷い〉
つくづく「有能」でなくて良かったと胸をなで下ろした。まるで「帰国子女」の扱いである。
さてここまで書いて、沖縄社会の同調圧力や出戻り組への冷たい仕打ちは、沖縄に限らず程度の差こそあれ、日本社会が抱える問題でもあることに気が付いた。樋口氏も【第5章 キャンドルサービス】の中でそのことに触れ、さらに【おわりに これからの沖縄の生きる道】で、その解決策にも言及している。ネタバラシになるので詳しくは本書をお読みいただきたい。
本書の読後感は、26年前にオランダ人のジャーナリスト、カレル・ヴァン・ウォルフレン氏が上梓したベストセラーに近い。それに因んで言うならば「人間を幸福にしない沖縄というシステム」。鋭い指摘が全編を貫くだけに、炎上……否、議論が沸騰するのは必至である。その指摘にどう対応するのか。沖縄の度量が試される。



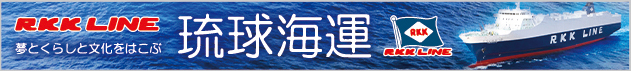



-1-150x112.jpg)










-1-150x112.jpg)
