それでも聖火を繋ぐ ランナーたちの思い
- 2021/5/13
- エンタメ・スポーツ

7月に開催予定の東京オリンピック・パラリンピックに向けた聖火リレー。「なぜ走る?」「即刻やめてしまえ!」と、毎日たくさんの言葉が飛び交っている。日本中が、世界中が新型コロナウイルスに翻弄され、東京オリ・パラの開催すら国会審議で紛糾し、一寸先もわからない状況が続いているが、それでも聖火は、今日も日本のどこかで灯されている。
沖縄では、5月1日と2日の2日間、石垣島以外は無観客で、178人がそれぞれの思いを胸に炎を繋いだ。筆者もその中の一人。ランナーたちの思いを現場で聴いた。
どんな環境でも全力を尽くす
そもそも聖火ランナーの選定基準は、組織委員会や自治体から推薦された人と、スポンサーの募集に自らの思いを込めた小論文を書いて応募し当選した人に分かれる。ニュースで報道される「辞退」した人たちはほとんど推薦されたメンバーで、小論文まで書いて当選した人たちとは少々思いが異なる。
5月1日、名護市民会館周辺で走行した高岡義泰さん(49)は、1972年生まれのいわゆる「復帰っ子」。「沖縄が益々平和であるよう、世界に平和を伝えたい」と応募した。少年サッカーの指導者でもあることから「コロナ禍を嘆くのではなく、どんな環境でも全力を尽くす、仲間と共に前に前へ」と希望を込めた。
琉球王府時代の髪型、うちなーかんぷーで走行した上間五月さん(30)は、幼少期から三線、琉球舞踊、空手を学んだエンターティナー。「自分に何ができるかを考えたら、沖縄の伝統文化を世界に伝えること。子々孫々まで大切な伝統を繋ぎたい」と沿道の三線の演奏に合わせて走行した。

55年間ずっと走りたいと願っていた
へき地巡回診療の体制を国内で初めて構築した徳里亜紀乃さん(39)は「日本は島国。海に囲まれた離島でも安心して希望を持って生きて欲しい」。と話す。当選の連絡を頂いた日に二人目の新しい命を宿していることがわかり妊婦で走る予定も、延期により出産してからの走行、母として希望の光を繋いだ。
5月2日、糸満市平和公園内の走行となった宮城直久さん(70)は、中学生だった1964年の東京オリンピックの聖火リレー隊列を、沿道から見ていたひとり。現在、消防士を退任し、救急ボランティアとして子供たちに遊びの中から危険、安全を教えている。「55年間ずっと走りたいと願っていた。希望を持って諦めないことで夢が叶った。今後は子供たちに夢を伝えていきたい」と次の目標を語った。



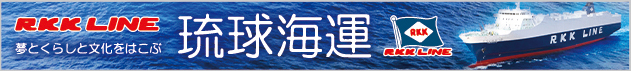














-1-150x112.jpg)
